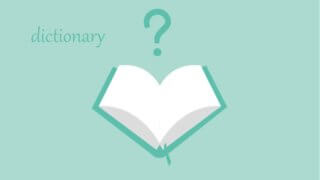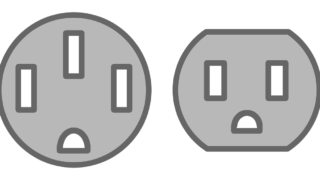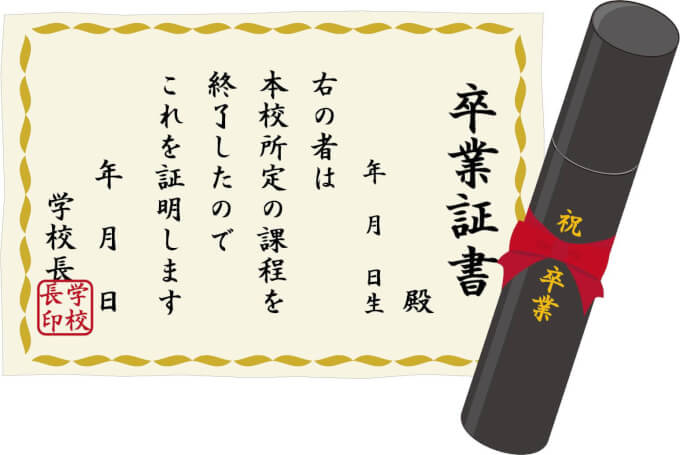先日、学校の宿題で出された算数のプリントが返ってきました。
プリントの内容はというと、今まで習った3年生の算数を確認するプリントだったのですが、息子が間違ったところを見てみると、距離に関する問題につまずいていました。
問題は、「Aさんの家から学校までのきょりは何mですか?」というものだったのですが、その1問と答えを見た限りでは、息子の答えが何で間違いなのかが不明でした。
でも、その次の問題をみたらすぐに謎が解けました。
今回は、小3の算数で習う「距離と道のりの違い」について例題を通してまとめてみました。
距離とは?道のりとは?
小3の算数では、「距離」と「道のり」の違いはこのようになっています。
|
距離=まっすぐにはかった長さ 道のり=道にそってはかった長さ |
例えばこの下図でいうと

「距離」とは、A点からC地点までといった2点の間を測る「直線距離」を指します。
「道のり」とは、A点 B点 C点を合わせた「道なりの距離」を指します。
では、例題です。
<問題>下の絵地図を見て答えましょう。

| 【問1】Aさんの家から学校までのきょりは何mですか? |
【答え】800m
【解説】
これは「距離(きょり)」を求める問題です。
「距離=まっすぐにはかった長さ」なので、A点からC点の長さを答えます。
A点からC点までのまっすぐな長さは800mなので、答えは 800m となります。
| 【問2】Aさんの家から学校までの道のりは何mですか? |
【答え】950m
【解説】
これは「道のり」を求める問題です。
「道のり=道にそってはかった長さ」なので、「A点 ~B点」と「B点~ C点」を合わせた長さを答えます。
「A点からB点」= 250m
「B点からC点」= 700m
250m+700m=950m
だから答えは 950m になります。
距離 速さ 時間の問題になると
高学年になると、「み は じ」「き は じ」の公式でおなじみ速さを出す問題が出てきます。
車や足で道路を走ったり、歩いたりするときの速さを出す問題ですね。
小3では「道のり」と「距離」の違いがはっきりとしていましたが、高学年になるとちょこっと変わっていきます。
実はこの速さの問題が出てくると、「道のり」と「距離」は同じ意味で使われていくようになるんですね。
道路って必ずしも「まっすぐじゃない」から「道のり」が正しい表現のような気もするのですが、問題では「距離」って言ってみたり「道のり」って言ってみたりします。
「道のり」と「直線距離」とするなら、違いがはっきり分かるのですが…。
日常生活では、「道のり」と「距離」はほぼ同じ意味で使われています。
だから、大人が久しぶりに小3の問題をとくと「アレっ?」となるんですが、コレって私だけでしょうか?
数学での距離の意味
中学に入ると算数から数学へと変わりますが、数学では「道のり」という言葉はほとんど使われないようになっていきます。
「距離=道のり」って言っても、いいかもしれません。(高学年以降は!)
「距離」に関する用語って、中学に入ると今度は「点と線の距離」という言葉が出てくるみたいですね。
中1の数学に登場するんだとか。
意味としては「点から線までの垂直の長さ」を指すらしいです。

これは垂直の線でまっすぐな線だから「点と線の距離」はしっくりきますね。
ところで、「点と線の距離」なんて、昔ありましたっけ?
私が中学生の時には無かったたような気がするのですが…。
忘れてるだけかな?
そしてこの「点と線の距離」ですが、これは高校の数学に登場する「点と直線の距離の公式の証明」へとつながっていく?っぽいです。
私は文系だったので習っておらず詳しいことは分かりませんが…。
なんか難しそうです…。
【▼この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます】

まとめ
小3の算数で出てくる「距離」と「道のり」の違いとは
距離=まっすぐにはかった長さ
道のり=道にそってはかった長さ
でした。
高学年以降は、道のりは距離として表現されていくけど、厳密には「道のり」と「距離」は違います。
文章問題では、何を聞かれているのかを間違えないようにしないとしないといけませんね。