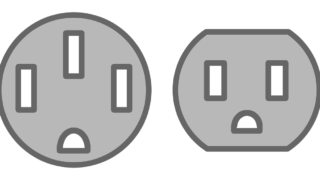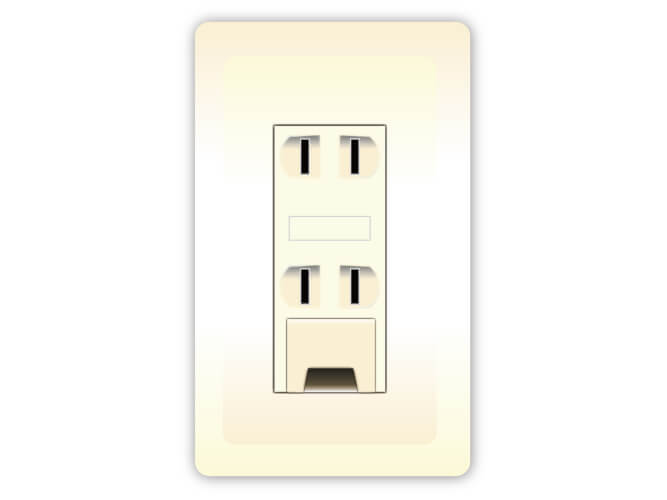突然ですが問題です。
「5こ分で1mになる はしたの長さは〇mでしょうか?」
あなたは分かりますか?
答えは、「分数」で答えるなら「1/5」です。詳細は後述しますね!
小学校の3年生になると、算数の問題に「はした」という言葉が出てきます。
私は先日、子どもに算数を教えていたのですが、算数プリントに出てきた「はした」という言葉の意味が分からず困ってしまいました。
そこで今回は、その時に学んだ算数に関する「はした」についてまとめてみました。
はしたの意味 算数では…
算数では、「0 1 2 3・・・」のようなぴったりの数を「整数」
「0.1 0.2 0.3」などのような半端な数(ぴったりでない数)を「はしたの数」といいます。
言い換えるなら、「1より小さい数」ですね。
そんな中途半端な数を表す「はした」ですが、「はした」という数は小数や分数という数字で表すことができます。
「0.1、0.2、0.3」などのように表した数字を「小数」といい、「1/2」「1/3」「 1/4」などのように表した数字を「分数」といいます。
はしたの表し方には小数と分数の2通りありますが、それは一体なぜなのでしょうか?
その理由は、「1÷3」の答えである「0.33333…」のような数は小数では表しきれないからです。
こういった数字は「1/2」「1/3」「 1/4」などのように「分数」で表さなければなりません。
はしたを表す数を小数や分数で表すと
では次に、「はした」と「小数」と「分数」の関係を、文章問題を通して見てみましょう。
<問題>
50cmの棒の長さを1mのものさしで測ったとします。
この50cmの棒は何mですか?
棒の長さを1メートルのものさしで1m単位で測るので、「小数」か「分数」で答えなくてはなりません。
はしたを表す数を分数で答えると
では、この問題を「分数」で答えるとどうなるでしょうか?
この50cmの「はした」は、1mものさしの半分くらい。
だから、棒を2つに分けたうちの1つ分なので 「1/2」
答えは、「1/2m」 になります。
もしくは、
50÷100=50/100=1/2 ですね。
はしたを表す数を小数で答えると
では、この問題を「小数」で答えるとどうなるでしょうか?
1mを10個に分けた場合、1目盛りは0.1m。
だから、棒を10個に分けたうちの5つ分だから 0.1×5で0.5
答えは、「0.5m」 になります。
はした7つ分で1リットルになるはしたのかさの答えは?
では最後に、はしたを求める問題を解いてみましょう!
< はした の練習問題(4問) >
①3こ分で1mになる はしたの長さを「分数」で表すと○m?
<答えは> 1/3mです。
<解説A>
1mを3こ分に分けるので、1÷3で 1/3m です。
<解説B>
1/3の「はした」の3個分は式で表すと、1/3 + 1/3+ 1/3= 3/3 = 1
②5こ分で1mになる はしたの長さは〇m?
<答えは>
分数なら 1/5m 小数なら 0.2m です。
③9こ分で1mになる はしたの長さを「分数」で表すと〇m?
<答えは> 1/9m です。
④はした7つ分で1Lになるはしたのかさを「分数」で表すと○L?
<答えは> 1/7L です。
はしたが算数で出てくるのはいつから?
「はした」という言葉が算数で出てきたのは、うちの子の学校の場合、小学校3年生の分数からでした。
私が小学生だったときは「はした」という言葉は無かったような気がするのですが、あなたが小学生の時は算数で「はした」という言葉は出てきましたか?
【▼この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます】

まとめ
『算数でいう「はした」とは、1より小さい半端の数の事で、はしたは小数や分数で表すことができる』
お子さんの算数プリントで「はした」が出てきたら、小数や分数で答える問題だと思いますので、どなたかの参考になれば幸いです。
この年になって今更なんですが、はしたの勉強を通して真分数と仮分数の名前の由来に気づいてしまいました。
真分数は「2/3」のような半端な数を表す分数だから、「真」に「半端」の「分数」で「真分数」で、仮分数は「5/5」のような切りのいい数も分数に表すので、「真」に「半端」の「分数」ではないから「仮」の「分数」で「仮分数」なんですね。
小学生の時は深く考えなかったので気づきませんでしたが、この年になって始めて気づきました。