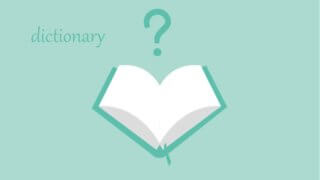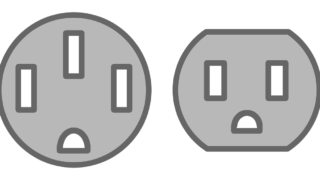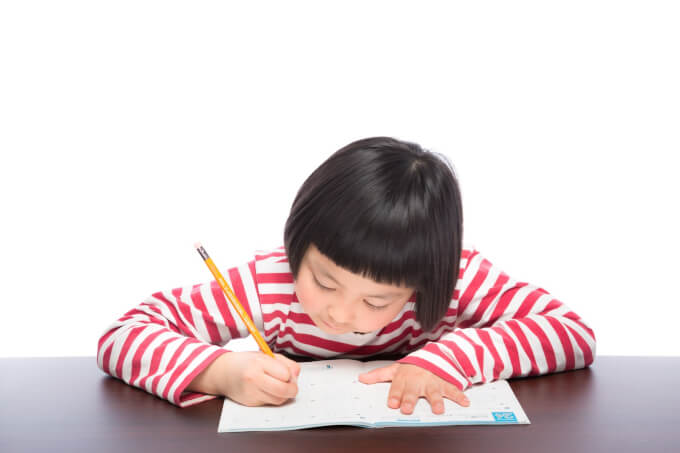小学生以上のお子さんがいるあなたに質問です。
もし子供から「なぜ宿題をするのか?」「宿題やる意味って何?」と問われたとしたら、あなたはその子どもの問いに対してすぐに答えられますか?
おそらく多くの人はこの問いに対して戸惑い、自信をもっては答えられないのではないでしょうか?
私もその一人です。
では、この様な「宿題の意義」について子どもから問われた場合、私たち大人はどのように答えたらいいのでしょうか?
そこで今回は、子どもに宿題をするメリットを伝えられるよう、
・「宿題をする意味」
・「宿題嫌い対策」
を私なりに考え、まとめてみました。
宿題が誕生した理由とは?
日本で宿題が誕生したのは、夏休みの制度が始まったことに由来しています。
日本では4月に新学年が始まると、勉強に慣れてきた約3カ月後には夏休みに入ってしまいます。
そのため、学業が中断することで子どもたちが授業の内容を忘れることのないようにとの考えから、いわゆる「宿題」が誕生したようです。
宿題をする意味とは?
宿題が誕生した由来にもあるように、宿題をする理由の一つには「学んだことを頭に定着させるため」という意味があります。
人間はその日に学んだ知識の74%は忘れてしまうといわれているので、知識を定着させるには何度も学ぶという事が必要になってくるんですね。
そのため、自宅でも学習を習慣づけることは、とても大事なこととなってきます。
「宿題はやるのが当たり前だから」
「みんながやってるから」
「宿題も勉強。勉強は子どもに必要だから」
などといったあいまいな答えでは子どもは納得しません。
だから子どもにはまず、宿題の本来の意味とは何かについて伝えたいですね。
授業理解度の確認
宿題の本来の意味には「勉強した内容を忘れないように」との意味がありますが、忘れる前の段階としてそもそも「勉強した内容を理解していること」も重要です。
勉強が得意な子どもは授業だけで理解ができてしまいますが、そうでない子どもは復習をしないと理解ができません。
だから宿題は、学習内容をより定着させるためだけにあるのではなく、
「学習内容を理解して、次の学習へ安心して進めるようにするため」
といった意義もあります。
だから宿題をすることは、「今日学んだ内容を理解すること」と「次の学習への準備」ともなっているのです。
自立するためには
子どもは大人になれば自分で考えて、計画して、行動していかなくてはなりません。
宿題は何分でできそうか、どのように課題を進めるか、いつやるべきかなどを自分で取り組むことで、子どもは自立する力が身についていきます。
つまり宿題は、自分で考えて行動していく力(自立)を身に着けていくためのものでもあるのです。
宿題に真面目に取り組んで得た結果、宿題をやらなかったことで得た結果。
それらを体験していくことが、子どもが将来より良く生きていくための知恵となるのです。
宿題嫌いにさせないためには…
子供が勉強嫌いになってしまう原因には、次のような宿題に関する問題点が関係しているかもしれません。
宿題の問題点とは?
〇学校の宿題は全員一律
学習の理解度やペースは一人ひとり違うのに、場合によっては勉強が苦手な子どもには課題の内容や量が多すぎてしまい、勉強嫌いを助長してしまいます。
〇親の負担
勉強を苦手とする子どもをもつ親は、毎日子どもの宿題に付き合わなければならず、場合によっては親にも子どもにも大きな負担となってしまいます。
〇習い事
宿題が負担になるのは勉強が苦手な子どもだけではありません。
現代では学習塾などが発展し、学習塾などの宿題が加わってしまうと、子供どもによっては大きな負担となってしまいます。
宿題嫌い対策
子供が宿題を進んでできるようにするためには、こんな工夫が有効かもしれません。
〇宿題の取り組ませ方を工夫してみる
宿題嫌いの子どもには、5分やったら5分休憩とか、ここまでやたらお気に入りのおやつをあげるなどの工夫が大切だと思います。
子どもが宿題に取り組まないために親が頭を悩ませてしまう場合は、一度、「勉強はこうするべき!」という固定概念を見直してみることも必要かもしれません。
〇宿題の量が子どもの能力に合っているのかを考えてみる
同じクラスのお子さんのお母さんに、そのお子さんが宿題に取り組んでいる様子を聞いてみると、そもそも宿題がクラス全員にとって多いのか少ないのか、自分の子どもだけが極端に宿題に取り組めていないのかなどの情報が分かります。
〇担任の先生に相談してみる
親がどんなに宿題をやろうと声をかけても、手伝おうとしても、なかなか宿題取り組もうとしないお子さんもいらっしゃると思います。
そんな時は何が何でもさせようとするのではなく、担任の先生に相談することも必要だと思います。
なぜなら、宿題に取り組めない背景には勉強が嫌いという気持ちの問題だけではなく、人間関係などの心理的な問題や発達的な問題がある可能性があるからです。
宿題をしない子には発達障害があることも
実は、私の息子は低学年の時、なかなか宿題に取り組むことができませんでした。
だから私は毎日毎日怒ってしまっていたんですね。
そしてその後、宿題がすべての原因ではありませんが、うちの息子は不登校になってしまいました。
学校や親から毎日怒られることで、自己肯定感が極端に低くなってしまったのかもしれません。
でも今は息子の特性に気づいてあげられたので、先生と相談しながら宿題に取り組ませています。
【関連記事】

まとめ
宿題をするメリットとは?
①学んだことを頭に定着させるため(知識の定着化)
②学習習慣を身に着けるため(学習習慣)
③自分で考えて行動していく力を身につけさせるため(自立)
④今日の学習内容を理解することと、次の学習への準備をするため(授業の理解)
ということになります。
これらを説明したからといって、子どもがすぐに納得してくれるとは限りませんが、勉強嫌いなお子さんが少しづつでも、勉強や宿題の大切さを理解してくれることを願っています。