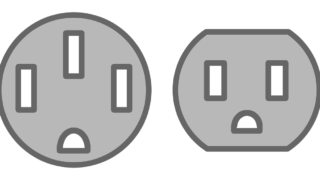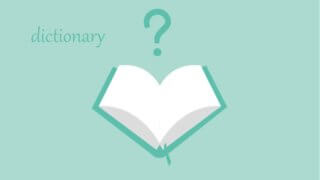うちの息子は小1の2学期から不登校になりました。1学期中はとにかく「学校へ行かせないと」という思いが強すぎて、私は強引に息子を登校させてしまったんですね。
だから、その疲れを癒してもらおうという想いと子どもの希望で、夏休み中は学童へいれることにしました。
しかし、お友達と遊んで元気になれればいいなと学童へ入れてみたものの、今度はこちらも拒否し始めてしまい、結局この学童は退所。
そのため、夏休み中はほとんど友人と遊べず、息子も学校へ行くエネルギーを十分に蓄えることができないまま2学期を迎えてしまい、やがて本格的な不登校となっていきました。
今回は、今だから分かる「登校渋りや不登校の子どもを待つとは」どういうことだったのかを、私の失敗談から考えたいと思います。
不登校の子どもを待つとは?
待つことを決断
息子の登校渋りは、2学期になっても相変わらずの状態でした。
そこで数日は付き添い登校をしてみたものの、結局私が付き添っても息子は学校が嫌だと拒否したため、付き添い登校という選択肢は無くなってしまいました。
その時の息子の精神状態はというと、1学期よりも悪い様子。
とても登校を促せる状態ではなくなってたので、私は学校にしばらくお休みすることを伝えて、子どもが元気になることを待つことにしました。
しかし、お休みするのはいいものの、家ではどうしたらいいのかよく分かりません。
「まったく勉強させないのもなぁ~」と思ったので、私はとりあえず本屋さんで問題集を買い、それを学校の日程表にあわせてするように促していました。
具体的には、国語の時間は漢字の問題や読み取り問題などを、算数の時間は計算問題などするといった感じです。
すると、当初の息子は嫌がることもなく素直に取り組んでいたのですが、慣れた頃からはだんだんと取り掛かりが遅くなっって、何かと理由を付けてはやらなくなっていきました。
待ち方の失敗
不登校を認め始めたころの私はというと、勉強のことが不安になってしまったので、勉強をさせることに力を入れ過ぎてしまいました。
ネットの情報でも、学校には行かないけど自宅で勉強している子が多くいるように感じたので、学校へ戻った時にもその方が負担が少ないだろうと、勉強をさせてしまったんですね。
もちろん、ゲームなどで遊ばせることはOKとしていたのですが、楽しそうに遊んでいる様子を見ると、学校をただサボってるように感じてしまい、私はイライラがたまっていきました。
だからつい、勉強もしないでゲームをしていると怒りを爆発させてしまっていたのですが、今はこれって間違いだったなと反省しています。
不登校の子どもを待つのはいつまで?方法は?
今だから分かるのですが、「不登校の子どもを待つ」ということの意味は、なんでもかんでも子ども任せで待つことでも、不登校に無関心になることでもありません。
子どもを待つとは、子どもの心が自尊心で満たされて、子どもが自分のタイミングで登校できるよう、その手助けをしながら「待つ」という努力をすることが、親にとっての「本当の意味の待つ」なんです。
「何もしない」ことが待つではないんですね。
勉強をさせることは本人の為になるからいいのではないか?と思ってしまうのですが、もし本人が嫌がっている場合は逆効果です。
やりたくない事に対して無理に取り組ませることは、自己否定を促してより不登校を長引かせることにつながってしまうかもしれないんですね。
それなのに当時の私はそのことに気づけなくて、学校を休んでいれば自然に元気になるだろうと休ませるようにはしたものの、今度は勉強のストレスを与えてしまいました。
もちろん、勉強をさせることは必要ですよ。
しかし、「勉強!勉強!」と勉強をすることを強制してしまうと、子どもは学校へ行けないことの辛さに加えて今度は、勉強にも取り組めない自分が加わることで、自分自身をダメな人間と思うようになってしまうのです。
うちの子はやがて、「僕はダメな子なんだ、生まれてこない方がよかったんだ」と、度々口にするようになってしまいました。
ほめる、認めることが大切
このままではいけない!!と感じた私はすぐに、勉強中心になりつつあった生活から遊び中心の生活に切り替えました。
そして、学校でのカウンセリングでは、子ども自身もスクールカウンセラーさんと遊びを通した活動(プレイセラピー)をスタート。
すると、子どもが少しづつ元気を取り戻し、別室登校ができるようになっていきました。
実は、こんなことになる前に私は「子どもが勉強もせずゲームしたり、遊んでばかりいるのが頭にくる。こんなことさせてていいのでしょうか?」とスクールカウンセラーさんに相談したことがあったんですね。
するとカウンセラーさんは、「子どもは遊びながら様々なことを学ぶんだからそれでいいんだよ!」と教えてくれていたんですが、当時の私はその意見を完全には取り入れることができなかったのです。
その事に気づいてからは「もう間違えたくない!」と、自宅では息子と一緒にゲームをしたり、料理をしたり、テレビを見たりする時間を増やしていきました。
そして時には息子と、息子が小さかったときのアルバムを見て、この時はああだったね!こうだったと!と、昔も今も息子がかわいい存在なんだと伝えました。
息子の優しいところや気が利くところなどを積極的に褒めるようにしたり、昔の息子も、今の学校へ行けていない息子も、大切な存在なんだということ伝え続けました。
▼関連記事

すると、自分を否定しがちだった息子がいつしか「僕は生まれてきて良かったんだね」と自分を肯定できるようになっていき、2年生の春に教室へ復帰しました。
▼関連記事

まとめ
待ち方の間違いに気づいて家での過ごし方のコツはつかめたものの、やはり人間ですから気持ちがブレてしまったり、息子とケンカになってしまったこともありました。
でも、そんな時には夫がフォローに入り、笑ったり泣いたりしながら数か月が過ぎた2年生の春、なんと息子は学校へ復帰。
まだ登校は不安定なところがありますが、これも個性のひとつとらえ、私は今も息子を応援しています。