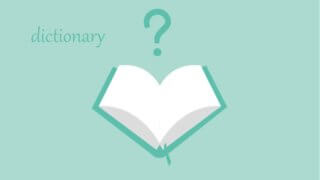私は先日、「ペアレントトレーニング」という子育て講座に参加したのですが、あなたはペアレントトレーニングという言葉を聞いたことがありますか?
このペアレントトレーニングとは何かというと、もともとは発達障害の子どもを育てる保護者への「子育て支援」&子どもへの「発達支援」を目的として生まれたものなんですね。
でも現在では、発達障害の子供だけではなく、育てにくい子どもの対応にも応用されています。
今回は、そんなペアレントトレーニング講座で学んだ「子どものほめ方」「25パーセントルール」についてお話ししたいと思います。
ペアレントトレーニングとは?まずは長所探しから始めよう!
私は2年くらい前に、たまたま地元で開かれたペアレントトレーニングの講座を受講したんですが、その講座ではまず、子どもの良いところを出来るだけくさん見つけるという事をしたのを覚えています。
講師 「お子さんの良いところを、まずは10コ書いてみましょう!」
私 「えっ!良いところ?」
「う~ん…」
こう言われたら、あなたは10コ書けますか?
ちょっと試してみてください。
…………。
…………。
…………。
どうですか?
10個書けましたか?
「えっ、書けないですか!?」
「でも、大丈夫ですよ!」
もし、たくさん見つからなかったとしても大丈夫なんです。
私が講座を受講した際には2~3個くらいしか出てきませんでしたし、他の方々も沢山は書けていません。講師の方も今までの経験上、たくさん書ける人は少ないと言っていました。
私たち人間は、良いところよりも悪いところを探す方が得意なんですね。だから、子どもの良いところをなかなか書けないんだそうですよ。
ペアレントトレーニングで褒めるスキルをアップさせるには?
子どもを褒めるという事は、子どもとの信頼関係を築くのに必要不可欠なものです。
子どもは親から褒められたり、認められたりすることで親を信頼し、自分に対しても「自分は自分でいいんだ」という自己肯定感を抱くことができます。
この自己肯定感が高い子どもというのは、常に気持ちが安定し、もし、何かにつまずくようなことがあっても簡単には凹みません。
逆に、怒られたり、否定ばかりされた子どもというのは、この自己肯定感が育ちにくく、気持ちが不安定で、問題行動を起こしやすくなってしまいます。
上手に褒めるためには、まず褒めるべき行動を分ける必要があります。
▼関連記事
息子は落ち着きのない男の子。ADHDを疑い、育児方法が変化した私
行動を分ける

ペアレントトレーニングでは、子どもの行動を「好ましい行動」「減らしたい行動」「無くしたい行動」の3つに分けて考えます。
そして次に「減らしたい行動」や「無くしたい行動」をしたときの「代わりにとって欲しい行動」を考えます。
どういうことかというと、例えばうちの子の場合、息子は家の中を運動場の様にして走り回ったりしていたので、私はそれを改善したいなと思っていました。
だからこの場合
好ましい行動 =「家ではおとなしく遊ぶ」
減らしたい行動 =「家を運動場のようにして遊ぶ」
とします。
では、代わりにとって欲しい行動はどうしたら良いのかというと、多動の子の動きを激しく制限するのは難しいですよね。
だから私は、体をいっぱい動かせる部屋をあえて作り、そこにトランポリンと鉄棒とバランスボールをおいて、いつでもそこで遊べるようにしたんです。
そして、体をいっぱい動かしたいような時には、その部屋で遊ぶよう声掛けをします。
つまりこの場合、
としたのです。
子供に対してただ「大人しく遊びなさい」と怒るだけでは、なかなか解決しないこともありますよね。
それに、何度も激しく怒っって行動を変えようとする事は子どもの自己肯定感を低くさせ、他の問題行動をうながしてしまう可能性がありますから、代わりにとって欲しい行動を考えておくことは大切なのです。
▼関連記事
ADHDの子どもの対応や接し方の工夫とは? 我が家の8つの方法
ペアレントトレーニングは25パーセントルールでいこう!

代わりにとって欲しい行動を上手に促すためには、親子の信頼関係がとても重要です。
だから、子どもの「良いところ探し」と「褒めること」をまずはしっかりとする必要があるのですが、うちの息子は褒めるポイントが少なすぎて、私はどうすれば褒められるんだろうと困ったんです。
でもそれは私だけではなく、講座の参加者の多くが困っていたことで、そんな時に講師はこう言いました。
「褒めるのは、子どもが100%出来た時じゃなくてもいいんです」
「理想の25%を達成できていれば」
「その25パーセントを褒めてあげてください!!」と。
どういうことかというと、例えば子どもにお風呂の掃除を頼んだとします。
すると、子どもは親に言われた通りに「お風呂を洗ったよ」と言うので、お風呂を確認しに行きました。
すると、お風呂は洗ってはあるものの、泡がまだ落ち切っていないことが判明・・・。
こういった場合、多くの親は「洗えてないじゃないか!」と怒ると思うんですよね。
「もっとちゃんと綺麗に洗いなさい」と。
確かにこの状態では、大人の思う「洗えているという状態」ではありません。
だから100点満点ではないんですね。
しかし、この子どもは「洗った」のです。
つまり、25パーセントを褒めるという事は、「洗った」「洗ってくれた」という
「出来ている行動」に注目してそこを「褒めましょう」という事なんです。
▼関連記事
話が噛み合わない子ども。話が噛み合わない理由は認知の歪みかも!?
出来ていることに注目する

これを聞いた時、私は「なるほど~!!」と目からうろこ状態でした。
褒めるハードルはもっともっと下げてあげればいいんだと気づきました。
例えば、鉛筆さえ持とうとしない宿題嫌いの子どもには「宿題しなさい(怒)」ではなく、
ちょっとでも宿題に取り組もうとしたら「やる気を出せたね」とまずはすぐに褒め、鉛筆を持てたら「鉛筆持てたね」と、またそれを褒めてあげればいいんです!
また、食事中に食べ歩く子どもなら、座って食べられている時に「座って食べられているね」と、すぐ褒めてあげればいいんですよ!!
この25パーセントルール、私は最初うまくできなかったんですが、出来ていることに注目するように意識していたらだんだん慣れてきて、褒め上手になってきました。
▼関連記事
ペアレントトレーニングで挫折をしないために必要なこととは?
まとめ
25%ルール、あなたはどんな風に感じましたか?
うちの息子は出来ないことが本当に多いので、このルールを知る前は怒ってばかりいました。
でもこのルールを学んでからは「出来ていることに注目する」クセがついて、子どもを褒めやすくなり、子どもの問題行動も減りつつあります。
この25%ルールは、夫婦関係などの人間関係にも応用できますので、よかったらぜひ試してみてくださいね。